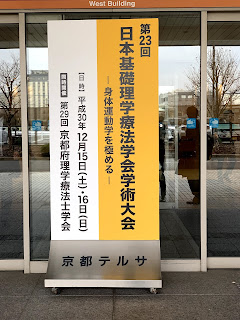本日紹介させていただく文献は肩関節インピンジメント症候群をX線学的に検討しているものです。
杉本勝正他:肩インピンジメント症例のX線学的検討.肩関節13(2),1989:214-217
目的は肩峰の傾きや形状より、変性の強い前外側部の3次元的位置関係がimpingement発症に少なからず関与していると考え、正常群とimpingemnet症例群の肩峰前方部の空間座標を求め比較検討することです。さらに骨頭や大結節なども含めた相対的な大きさも発症要因となりうると考え、骨頭と肩峰、骨頭と大結節の大きさの比を計測しています。
対象はimpingement症例と診断された10例15関節、正常群7例14関節です。
CT撮影を行い座標を用いて検討しています。
結果はimpingement症例では正常群に比し前下方の位置していました。acromionの形状がより前下方に位置ししている症例においてimpingementが起こりやすいことを示していると考えられたとと述べています。また、肩峰が骨頭をより大きく覆っている症例や、相対的に大結節が骨頭より大きい症例にimpingement発症例が多い結果となりました。これは日常生活においてanterior pathによる挙上を行うため、大結節や肩峰が相対的に大きな症例ではその過程でimpingementの機会が物理的に多くなると思われたと述べています。今回の検討で正常群とimongement群で肩峰傾斜はあまり差がなかったと報告しており、肩峰傾斜はimpingementにあまり関与していると考えられたと述べています。
骨の形状に関しては運動療法で変えることができません。
インピンジメント症例に対して形状以外にどのような要因があってきれいにC-Aアーチを大結節が通過しないのか理学所見を元に検討していく必要があると感じました。
Staff profile
COVID-19(新型コロナウイルス)感染拡大予防に対する対応について
整形外科リハビリテーション学会は、オンライン開催または感染対策を徹底した上でのハイブリッド開催により、定例会、学術集会、特別講演会、シンポジウムを開催して参ります。なお、技術研修会につきましては、再開の目処が立っておりません。理事会の決定があり次第、ウェブサイトならびに当ブログにてご報告させて頂きます。
2018年12月31日月曜日
2018年12月29日土曜日
【文献紹介】肩峰下圧の動態計測について
本日紹介させて頂く文献は肩峰下インピンジメント症候群に関する論文です。
橋下淳ら:肩峰下圧の動態計測.臨床スポーツ医学vol.15,No.3,1998:263-266
この論文では、肩関節に対して観血的治療を行った患者260人を対象に、麻酔下にて肩峰下滑液包内に圧計測用のバルーンカテーテルを挿入した状態で肩関節の運動(前方及び肩甲骨面上の挙上及び下降、下垂位内外旋、肩90度外転位での内外旋)を行い、その時の肩峰下圧の計測を行われています。
結果、前方挙上と肩甲骨面挙上では後者の方が変動は少ないが、ほぼ同様の圧変化を示し、80度から圧が高まり始め130度から最大挙上にかけて圧が高くなるとされています。
下垂位内外旋では圧はほとんど変動せず、90度外転位での回旋では外旋では圧はほぼ変化せず、内旋では圧が著名に変化し、前方挙上時の約2倍の圧がかかるとされています。
また挙上に関しては30%の症例に関節拘縮や腱板や肩峰下滑液包の癒着を認め、この群は、肩90度外転位での内旋時と同程度の圧上昇を認めたとのことでした。
考察では、肩峰下インピンジメントでは、最も病態の進行したとされる腱板断裂でも肩峰と骨頭が直接衝突している実証はなく、滑液包内の圧が変動するだけで、腱板が挟まれている可能性は少ないことが考えられるとしています。
この論文を通して考えると、インピンジメント症候群と診断されている症例のなかでも単に肩峰と上腕骨の衝突と考えるのではなく、どの組織の圧が高くなっているのか、その圧を高める要因がどの組織にあるのかを考えなければいけないと思いました。
投稿者:小林 駿也
2018年12月25日火曜日
【文献紹介】膝関節屈曲動作時の膝周囲の皮膚の伸張性について
今回は、膝関節屈曲動作時に皮膚組織がどれだけ伸張されているのかを研究された文献を紹介させていただきます。
和田直子他:膝関節屈曲動作時の膝周囲の皮膚の伸張性について.関西理学.12:41-44,2012
対象は整形外科学的および神経学的に問題がない健常者30名の右下肢を用いて行われており、それぞれの膝関節に伸展位にて脛骨粗面から膝蓋骨尖までの距離を基準距離とし、計5か所にマーキングを行い、足底が床面に接した状態で膝関節を他動的に屈曲30°位、60°位、90°位、120°位、150°位、最大屈曲位と設定されていた。また、それぞれの角度による皮膚の伸張性を測定されていました。また各部位において以下のように伸張差と伸張率を算出していました。
伸張差(各屈曲角度間における距離の差)(mm)
=(求める屈曲角度での距離)-(求める屈曲角度-30°の屈曲角度での距離)
伸張率(伸張差を基準距離と比較した割合)(%)
=伸張差/基準距離×100
結果は、各々の角度で皮膚の伸張は見られたが、全ての部位(大腿部、膝蓋上嚢、膝蓋骨部、膝蓋靭帯部)において屈曲0°から30°で有意に皮膚の伸張率が増加したと述べています。
膝関節周囲の疾患に対しての手術を施行した際、可動域制限の一つとして、皮膚の伸張性が挙げられる場面も多々あると思います。今回の研究から、どの肢位で皮膚の伸張性が得られやすく、アプローチする軟部組織を明確にすることで皮膚の伸張性の低下が防げるのではないかと考えました。
皮膚組織の拘縮予防は、術後急性期に行う重要な理学療法の一つと言っても過言ではないでしょう。皮膚や皮下組織の拘縮はROMの制限因子になる可能性が大きいため、今回の文献で皮膚組織の拘縮予防の重要性が再確認できました。
投稿者:高橋 蔵ノ助
2018年12月24日月曜日
【文献紹介】肩腱板断裂における上腕骨頭位置の解析
本日紹介させていただく文献はX線を用いて腱板断裂症例における骨頭の位置を検討したものです。
山口拓嗣他:肩腱板断裂における上腕骨頭位置の解析.肩関節18(1),1994:95-98
腱板断裂が骨頭支持及び安定化機構としての役割を明らかにすることを目的としています。
対象は腱板断裂が診断された45例46肩、コントロール群として健常成人56例56肩としています。
方法はX線撮影は内外旋中間位と45°外旋位でY viewを撮影します。各座標を定め解析しています。(A:臼蓋中心、B:骨頭中心、C:骨頭頂点、D:烏口突起先端、E:肩峰先端、F:肩峰角、G:肩甲棘と烏口突起基部の交点)
結果はコントロール群では中間位から外旋位で後方やや下方へ移動し、腱板断裂群では単純に下方へしており、移動量は少ない結果となりました。また、DE(CAアーチ)から骨頭中心、EF(肩峰下面)から骨頭中心まで距離を計測すると、中間位、外旋位ともに断裂群のほうが値が小さく、距離が短くなる結果となりました。
腱板は骨頭の求心位を保持する役割があるが、大胆列でも骨頭の上昇、後方移動が見られない症例も多数いました。
断裂群を断裂の大きさで2群に分けて比較すると、棘上筋断裂ではコントロール群と近似した分布を示し、大断裂では分散した結果となりました。
さらに他動挙上90°可否にて2群に分けて検討すると拘縮症例にて有意に上方へ偏位していました。
安静下垂位の状態で腱板が作用しているとは考え難いと述べており、安静位下垂位で骨頭が上方偏位している症例位は、断裂した状態で活動を繰り返すこと後上方拘縮した症例だけが骨頭の上方例として見られると考察しています。つまりAHIを下垂時で検討しているものは断裂そのものよりもそれに引き続き起こる拘縮を見ていることになると述べています。
臨床上、画像所見より肩峰骨頭間距離を確認することは非常に多いと思います。今回紹介させていただいた文献から下垂位の状態ですでに骨頭が上方に偏位している症例においては拘縮が疑われることが分かりました。
山口拓嗣他:肩腱板断裂における上腕骨頭位置の解析.肩関節18(1),1994:95-98
腱板断裂が骨頭支持及び安定化機構としての役割を明らかにすることを目的としています。
対象は腱板断裂が診断された45例46肩、コントロール群として健常成人56例56肩としています。
方法はX線撮影は内外旋中間位と45°外旋位でY viewを撮影します。各座標を定め解析しています。(A:臼蓋中心、B:骨頭中心、C:骨頭頂点、D:烏口突起先端、E:肩峰先端、F:肩峰角、G:肩甲棘と烏口突起基部の交点)
結果はコントロール群では中間位から外旋位で後方やや下方へ移動し、腱板断裂群では単純に下方へしており、移動量は少ない結果となりました。また、DE(CAアーチ)から骨頭中心、EF(肩峰下面)から骨頭中心まで距離を計測すると、中間位、外旋位ともに断裂群のほうが値が小さく、距離が短くなる結果となりました。
腱板は骨頭の求心位を保持する役割があるが、大胆列でも骨頭の上昇、後方移動が見られない症例も多数いました。
断裂群を断裂の大きさで2群に分けて比較すると、棘上筋断裂ではコントロール群と近似した分布を示し、大断裂では分散した結果となりました。
さらに他動挙上90°可否にて2群に分けて検討すると拘縮症例にて有意に上方へ偏位していました。
安静下垂位の状態で腱板が作用しているとは考え難いと述べており、安静位下垂位で骨頭が上方偏位している症例位は、断裂した状態で活動を繰り返すこと後上方拘縮した症例だけが骨頭の上方例として見られると考察しています。つまりAHIを下垂時で検討しているものは断裂そのものよりもそれに引き続き起こる拘縮を見ていることになると述べています。
臨床上、画像所見より肩峰骨頭間距離を確認することは非常に多いと思います。今回紹介させていただいた文献から下垂位の状態ですでに骨頭が上方に偏位している症例においては拘縮が疑われることが分かりました。
2018年12月23日日曜日
【文献紹介】無症状者における腰椎MRIの前向き調査
本日は無症状者における腰椎MRIの前向きに調査について、論文を紹介させて頂きます。
この研究では、腰痛、坐骨神経痛、または神経性の間欠性跛行を経験したことがない67名の健常者に対して脊椎のMRI検査を実施しています。スキャンは、被験者の臨床症状の有無について知識のない3人の神経放射線科医によって独立して解釈されています。
結果、被験者の約3分の1が実質的な異常を有することが判明しました。60歳未満の人のうち、20%が椎間板ヘルニア、1人は脊柱管狭窄症でした。60歳以上のグループでは、スキャンの約57パーセントで所見が異常を示していました。対象の36パーセントが椎間板ヘルニアを、21パーセントが脊椎狭窄を示しました。29〜39歳の被験者の35%、および60〜80歳の被験者のうちの1人を除く全員において、少なくとも1つの腰椎レベルの椎間板の変性または膨隆がみられたと述べられています。
無症候性の患者におけるこれらの所見を考慮して、MRI所見の異常は、手術治療が企図される前に、年齢およびあらゆる臨床的徴候および症状と厳密に相関しなければならないと結論づけています。
これは、脊椎のみにいえることではなく、その他の関節においても同じことが言えると考えます。肩では無症候性の腱板断裂、下肢では股関節唇損傷や半月板損傷などでも画像上では構造的破綻を認めますが臨床症状とマッチングしないことがあります。
画像所見は病態を推察する上で重要な情報となりますが、画像所見にとらわれて先入観をもって評価をしてしまうと隠れている病態を見落としてしまい、カンファレンスの中で指摘を受けることも多く経験します。
問診、画像所見、理学所見など様々な所見を統合し病態解釈を行っていくことを意識して毎日の臨床を大切にしていきたいと思います。
理学療法士の中では動作や姿勢を観察、分析して機能障害を推察するトップダウン評価が推奨されていることもあるそうですが、それだけでは何かを見落としてしまう可能性も考えられます。
動作をみることは重要な所見となりますが、あくまで1つの所見であり他の所見と統合し病態を推察することが重要と考えます。
投稿者:大渕 篤樹
2018年12月22日土曜日
【文献紹介】肩関節外転運動での生体3次元、関節上腕靭帯の機能長評価
本日は肩関節外転運動での生体3次元、関節上腕靭帯の機能長評価についての文献を紹介させて頂きます。
この論文では、mid range motionにおける生体内での関節上腕靭帯の変化を調査することを目的にされています。
方法は、生体内3次元動態解析システムおよび関節上腕靭帯の解剖研究から、肩関節外転運動における上肢自重下での関節上腕靭帯の3次元距離を計測し、動態に伴う距離変化を評価されています。
結果ですが、肩関節外転0°から60°まではSGHLが機能し、外転60°から90°ではMGHL、外転90°以上ではAIGHLが関節安定性に寄与していたとされています。
この論文の結論としては、mid range motionにおいては、各GHLが連動しながら、これら3つのGHLが異なる外転肢位でそれぞれが機能し肩甲上腕関節の安定性に寄与すると述べています。
この論文では肩関節不安定症に焦点を当てて、関節包靭帯の研究をされていますが、肩関節拘縮の症例を考える際にも必要な情報であると感じました。
上肢を挙上する際には骨頭が下方に下がる必要があり、この動きを制限する一つの組織としてIGHLが考えられますが、このIGHLが拘縮しており外転90°までの可動域を獲得できていなければ骨頭の下方への動きは制限されます。そのため、外転90°をいかに肩甲上腕関節で獲得出来るかは挙上に必要な要素であると考えています。
肩関節症例では評価・治療に難渋することが多く、解剖学的背景をもとに治療プランを立てていくことがより良いアプローチにつながることは日々実感させられます。今後も治療につながる幅広い知識、技術を日々の臨床から身につけていきたいと思います。
投稿者:小林 駿也
2018年12月21日金曜日
【文献紹介】拘縮肩における肩峰下滑液包内病変の影響について
本日は拘縮肩におけるSAB内病変が運動時痛や可動域制限に及ぼす悪影響の割合をSAB造影検査を用いて評価検討された論文を紹介します。
対象は6ヶ月以上の保存療法でも軽快を認めず、関節鏡視下関節包切開術を必要としたFrozen phaseの拘縮肩群38例38肩です。(拘縮の定義:麻酔下90度外転位での最大外旋および内旋の可動域の合計が120度以下)また明らかな拘縮を認めず、SAB病変が主病変と考えられる肩峰下インピンジメントを認める95例95肩を非拘縮群とし比較対象とされています。
造影剤を含む局所麻酔剤をSAB内に注入されており、評価項目は運動時除痛効果(VASの改善割合)、造影剤注入前後の自動可動域と他動可動域の改善角度です。
結果、運動時除痛効果は拘縮肩群では平均59.9%、非拘縮肩群では平均79.9%得られ、拘縮肩群で有意に低い除痛効果が認められたと示されていました。また他動可動域では拘縮肩群で屈曲平均14.5度、外転平均22.1度の可動域改善が得られ、拘縮肩群で有意に高い可動域の改善を認めたと示されていました。自動可動域では可動域の改善は認めたものの両群間に有意差は認められていませんでした。
拘縮の有無に関わらず約60~80%の割合で疼痛の原因としてSABが関与していたため、SABの炎症所見や周囲組織の癒着など理学所見や画像所見から評価し、見落とさないことが疼痛や可動域制限の改善をする上で重要であると思いました。
2018年12月19日水曜日
【文献紹介】踵骨骨折の術後早期荷重について
本日は踵骨骨折の術後早期荷重について報告されている文献を紹介させていただきたいと思います。
鄭ら:踵骨骨折の手術後早期荷重 骨折 第29巻,No.3 2007.
この文献では踵骨関節内骨折をプレート固定された31例を対象とされています。
この症例を海綿骨欠損部を補強しないで6週間免荷した群、欠損部を人工骨補填材で補強し6週間免荷した群、人工骨補填材で補強して3週間免荷した群の3群に分け術後の経過を追われています。
各群ベーラー角は術前から術後で大きく変わっています。
ベーラー角の術後と観察時の値の差は
6週荷重群で平均4.0°、6週補強群で平均2.6°、3週荷重群で平均0.5°であったと報告しています。
この文献から踵骨骨折後に荷重によるベーラー角の変化の仕方が分かりました。
この文献では海綿骨欠損部をどの材料で補うかも検討されていますが、私はこの文献を読み、プレート固定でかつ海綿骨欠損部を人工骨で補ってもベーラー角が変わることに注目しました。
6週間の免荷をしても仮骨形成が十分でない症例もおり、転位してきていることを考えると荷重のタイミングが難しいのではないかと思いました。
私も臨床で踵骨骨折の症例をみる機会がありますが、経皮ピンニングで固定されている症例、人工骨で欠損部を補っていない症例などの荷重には十分仮骨の状態を見極めアプローチする必要があると思いました。
明日からの臨床で活かせるよう勉強していきたいと思います。
投稿者:天鷲翔太
2018年12月18日火曜日
【文献紹介】肩インピンジメント症候群の肩峰下滑液包鏡視所見とMRI所見の比較検討
今回は腱板断裂を認めない肩インピンジメント症候群の肩峰下滑液包(SAB)鏡視所見とMRI所見の関係性を検討されている文献を紹介させていただきます。
佐々木誠人他:肩インピンジメント症候群の肩峰下滑液包鏡視所見とMRI所見の比較検討:整形外科と災害外科:49(1).149-152.2000
対象は肩インピンジメント症候群と診断され、術前MRI検査後に関節鏡視下肩峰下滑液包除圧術を施行され、術後3ヶ月以上の経過観察を行われた治療効果が得られた男性24肩女性16肩(平均年齢49歳)です。
肩峰下滑液包鏡視所見から、筆者は以下の3つのタイプに分けられています。
・肩峰下面摩耗型(27肩)
肩峰下面を中心に鳥口肩峰アーチ下に摩耗所見があるもの
・腱板炎型(10肩)
腱板上面の摩耗や肥厚があるが肩峰下面の摩耗所見が明らかでないもの
・烏口肩峰靭帯(CAL)肥厚型(3肩)
肩峰側と腱板側で摩耗所見が明らかでないが、烏口肩峰靭帯の肥厚を認めるもの
MRIは斜位前額面と斜位矢状画像にてT2starにて評価されており、いずれかで明らかな高輝度変化が見られるものを所見ありとされ、SAB部と腱板部を調べられています。
結果ですが、SABの高輝度変化の所見があったものは全体の80%、ないものが20%であり、腱板部に関しては所見があるものが18%、ないものが82%でありました。タイプ別でみると、肩峰下摩耗型ではSABが49%でSABと腱板両方が22%であり、所見なしが27%でした。腱板炎型ではSABが80%、両方が10%、所見なしが10%であり、CAL肥厚型ではSABが100%でした。
肩峰下インピンジメント症候群は鳥口肩峰アーチとSAB・腱板との間で生じる衝突現象とNeerが提唱しており、解剖学的破綻と機能的破綻から疼痛が生じるとされています。これらの病態が根本にあることからも、本研究は病態に基づいた結果が導き出されたのではないかと思われます。また、どのタイプにおいてもSABが高輝度になっていたことから、SABへの過度なストレスが大きな原因であることもわかります。
このことから、やはり肩峰下インピンジメント症候群症例に対しては、SABへのストレスを軽減させることが治療時の第一選択になるのではないかと考えられます。そのため、SABにストレスがかからざるを得ない軟部組織の状態を評価することが重要になるため、今後の臨床では再度軟部組織の評価を事細かに行うことを再確認できました。
投稿者:高橋 蔵ノ助
2018年12月17日月曜日
第29回京都府理学療法士学会、第6回日本運動器理学療法学術大会
昨日より2日間、第29回京都府理学療法士学会が行われ、当院からは茂木孝平先生が発表されました。
関節鏡手術後に下腿全面痛を呈した一症例
−膝関節拘縮と下肢malalignmentにより出現した疼痛の解釈ー
昨年開催されました第28回京都府理学療法士学会で当院の大渕篤樹先生が発表された「術前からの歩行時痛が残存していた腰部脊柱管狭窄症の一症例」が最優秀賞に選ばれ、会の中で表彰していただきました。
また、同日程で開催されました第6回日本運動器理学療法学術大会には当院から為沢一弘先生と中井亮佑先生が発表されました。
小殿筋の組織弾性が股関節可動域に与える影響について
人工膝関節全置換術後の膝関節屈曲可動域と膝蓋骨位置の特徴について
2018年12月12日水曜日
【文献紹介】MRIを用いた肩鎖関節と胸鎖関節の運動学的解析について
本日はMRIを用いた肩鎖関節と胸鎖関節の運動学的解析について報告されている文献を紹介させていただきたいと思います。
竹井ら:MRI(磁気共鳴画像)を用いた水平面における肩関節の肢位の変化による肩鎖関節と胸鎖関節の関節運動学的解析 J
Jpn Health Sci Vol.13,No.2 2010.
この文献では健常女性13名で背臥位にて上肢を体側につけた肢位を基本肢位とされています。
そこから①肘関節90°屈曲位での肩関節90°屈曲位 ②①から上肢帯最大前方突出位 ③②から肩関節最大水平屈曲位
この3つを行いMRIを撮影されています。
①から②になる、前方突出においては肩鎖関節よりも胸鎖関節の運動が主体となることが報告されています。
②から③になる、水平屈曲運動では胸鎖関節よりも肩鎖関節の運動が主体であることも報告されています。
この文献の報告から肩関節の水平屈曲時、前方突出時の鎖骨、肩甲骨の運動が分かりました。
関節運動は実際にどのように運動しているのかわかっていないと理学療法時にもうまく運動を誘導できないと思います。
より技術を身に付けていくためにも知識を付けていこうと思いました。
投稿者:天鷲翔太
【文献紹介】内側半月中後節移行部横断裂のMRI所見
今回は膝関節内側半月板中後節移行部横断裂時のMRI所見において、特徴的な所見が無いかを検討されている文献を紹介させていただきます。
本山達男他:内側半月中後節移行部横断裂のMRI所見. 整形外科と災害外科.65(2).199-202.2016
MRI所見読影の基準として、冠状断はT2、矢状断はプロトン強調像にて撮像された画像で行われており、51例51膝の内側半月板中後節移行部横断裂と診断された症例の術前MRIにて検討されています。
冠状断で最も多かった所見は、中後節移行部のスライスで正常半月板を描出した後、後方へスライスを移動させると、内側半月板の大部分で高信号が描出されていました。その後さらに後方へスライスを進めると、再度正常半月板が描出されるというもので、全体の62.7%で認められていました。(下図参照 文献より引用)
矢状断に関しては、内側半月板辺縁を描出しているスライスで横断裂様の高信号が全体の52.9%で認められていました。
内側半月板中後節移行部の損傷は、後角損傷についで損傷頻度の高いとされており、正確な画像診断が重要と諸家の報告でも見受けられますが、特徴的なサインなどは確立されていません。
筆者は今回冠状断で大部分高信号を一時的に認めた部分をvanishing signと仮定し、同部位での画像診断の特定方法として考案されていました。
しかし、本研究の及第点として、感度は高いが特異度は低いという点でした。特異度とは “陰性のものを正しく陰性と示す” 値であることはみなさん言うまでもないでしょう。
つまり、MRIでは横断裂が認められたが、同部位の横断裂が関節鏡にて観察すると認められい可能性が大いに有り得るということです。
我々理学療法士は関節鏡にて自ら関節内の状態を把握することは不可能です。そのため、画像所見を駆使し、患者様の状態を把握するスキルがとても重要になることは、日々の臨床での痛感しております。
半月板に関しては有用な整形外科的テストも多数報告されており、諸家の報告では各検査の感度や特異度についても報告されています。
治療技術だけではなく、そこに至るまでの評価技術の一つとして、画像読影方法について知識を深めていく事の重要性を再認識することができました。
投稿者:高橋 蔵ノ助
本山達男他:内側半月中後節移行部横断裂のMRI所見. 整形外科と災害外科.65(2).199-202.2016
冠状断で最も多かった所見は、中後節移行部のスライスで正常半月板を描出した後、後方へスライスを移動させると、内側半月板の大部分で高信号が描出されていました。その後さらに後方へスライスを進めると、再度正常半月板が描出されるというもので、全体の62.7%で認められていました。(下図参照 文献より引用)
矢状断に関しては、内側半月板辺縁を描出しているスライスで横断裂様の高信号が全体の52.9%で認められていました。
内側半月板中後節移行部の損傷は、後角損傷についで損傷頻度の高いとされており、正確な画像診断が重要と諸家の報告でも見受けられますが、特徴的なサインなどは確立されていません。
筆者は今回冠状断で大部分高信号を一時的に認めた部分をvanishing signと仮定し、同部位での画像診断の特定方法として考案されていました。
しかし、本研究の及第点として、感度は高いが特異度は低いという点でした。特異度とは “陰性のものを正しく陰性と示す” 値であることはみなさん言うまでもないでしょう。
つまり、MRIでは横断裂が認められたが、同部位の横断裂が関節鏡にて観察すると認められい可能性が大いに有り得るということです。
我々理学療法士は関節鏡にて自ら関節内の状態を把握することは不可能です。そのため、画像所見を駆使し、患者様の状態を把握するスキルがとても重要になることは、日々の臨床での痛感しております。
半月板に関しては有用な整形外科的テストも多数報告されており、諸家の報告では各検査の感度や特異度についても報告されています。
治療技術だけではなく、そこに至るまでの評価技術の一つとして、画像読影方法について知識を深めていく事の重要性を再認識することができました。
投稿者:高橋 蔵ノ助
2018年12月11日火曜日
【文献紹介】橈骨遠位端骨折に対する保存療法・手術療法の比較検討
今回は橈骨遠位端骨折に対する保存治療と手術治療の比較について文献紹介させていただきます。
橈骨遠位端骨折に対する治療はロッキングプレートによる固定が中心であり、良好な成績が多く報告されています。ロッキングプレートを用いることにより骨折部位を解剖学的な整復する位置での固定が可能となります。しかし、保存療法にて整復を行わくても機能評価の結果は良く患者の満足度も高かったです。今回の文献では、手術によるロッキングプレート固定法、保存療法によるものの比較検討がされています。
方法
掌側ロッキングプレートによる固定を行った手術群
前腕ギプス固定にて治療を行った保存治療群
で比較されています。
評価
・画像評価
X線画像での volar tilt radial inclination ulna plus varianceを
①受傷時と②整復時もしくは手術時と③最終評価時
にて比較。
・機能評価
⑴手関節可動域
⑵Quick DASH-JSSH
を最終評価時に測定し検討
保存治療・手術治療のどちらにおいても、患者様に合わせた手段を選択し、またそれに伴いただただ可動域を出すのではなく患者様の生活背景を検討し、それに対し一番良い治療を行っていく事が大切になってくることを改めて再確認する事ができました。
青山広道ら:橈骨遠位端骨折に対する保存治療と手術治療の比較検討
骨折 第33巻 No.1 2011
2018年12月10日月曜日
整形外科リハビリテーション学会 シンポジウム2018
本日整形外科リハビリテーション学会シンポジウム2018が行われました。
今回のテーマはエコーの活用法でした。
午前中は4名のシンポジストの先生方のご講演でした。
1.エコーがこれまでの常識を覆す!
名古屋栄ペインクリニック 松本優先生
2.無視できなくなる!エコーから見える末梢神経
一社ひがし治療院 神山卓也先生
3.超音波エコーならその足底部痛の原因が分かる!
中部学院大学 鵜飼建志先生
4.Shear wave elastgraphyで迫る!"black box"の解明
名古屋スポーツクリニック 福吉正樹先生
午後からは第1回学術報告会が行われ、6名の先生が発表されました。
正しくアプローチできているのか、触れているものが本当にターゲットにしているものなのか、エコーで可視化することでより適切な運動療法が行うことができると思いました。
正しくアプローチできているのか、触れているものが本当にターゲットにしているものなのか、エコーで可視化することでより適切な運動療法が行うことができると思いました。
ただプローブを当ててもその下には何があり、画面にはどの軟部組織が写っているのか分からなければ意味がありません。
まずは解剖を理解し、描出した画像に何が写っているのか理解し、再度同じ絵を描出できる再現性も練習して獲得していく必要があると思いました。
当院にもエコーがあるのでもっと積極的にエコーを使っていこうと思いました。
まずは解剖を理解し、描出した画像に何が写っているのか理解し、再度同じ絵を描出できる再現性も練習して獲得していく必要があると思いました。
当院にもエコーがあるのでもっと積極的にエコーを使っていこうと思いました。
2018年12月7日金曜日
【文献紹介】保存療法を行った腱板断裂の疼痛関連因子について
本日は保存療法を行った腱板断裂の疼痛関連因子をMRIにより検討された論文を紹介します。
腱板断裂において保存療法で痛みが消失した症例と持続した症例のMRI所見を比較されています。対象はMRIで診断した棘上筋腱を含む症候性腱板断裂に対して注射や投薬による保存療法を行い、1年以上経過した時点でMRIを再検した96例108肩です。
MRI再検時の疼痛の有無を目的変数とし初回MRIの滑液腔の水腫、断裂の引き込み、肩甲下筋腱断裂、棘下筋腱断裂の有無、肩甲下筋、棘下筋、棘上筋の各Goutallier分類の7因子を説明変数として単変量ロジスティック回帰分析を行い、有意差を認めた因子を次の多変量ロジスティック回帰分析の説明変数とすることで初回MRIにおける疼痛持続の予測因子を調査されています。また最終MRIも同様の手順で疼痛残存に影響する因子を調査されています。
結果ではMRI再検時、疼痛は67肩で持続し41肩で消失しており、初回MRIにおける疼痛持続因子は肩甲下筋腱断裂のみに、また最終MRIにおける疼痛残存因子は滑液腔の水腫と肩甲下筋腱断裂で有意差が認められたと報告されていました。
考察では疼痛残存因子であった肩甲下筋腱はtransversal force coupleや上腕二頭筋長頭腱の安定性に寄与するため重要であると述べられていました。
臨床上、画像所見から得られる損傷組織が痛みの出現部位とは限らないので、理学所見から疼痛の出現部位を特定するとともにその部位にどんなメカニカルストレスが加わっているのかを理解することが大切だと思いました。
投稿者:佐々木拓馬
2018年12月5日水曜日
【文献紹介】肩甲骨の加齢による可動域の変化について
本日は肩甲骨の加齢による可動域の変化について報告されている文献を紹介させていただきたいと思います。
田中ら:肩甲骨の加齢による可動域の変化についての検討 The Shoulder Joint,Vol.19,No.1,118-122,1995.
この文献では3才、5才幼児46名、30代男性20名、60代男性23名を対象にされています。
水平屈曲、伸展を行わせ、外転90°、屈曲90°、最大水平屈曲位で上肢と左右の肩甲棘のなす角度を測定されています。
各動作で幼児、30代、60代の順に角度が減少していることが報告されています。
この文献から加齢により肩甲骨可動域が制限されていくことが分かりました。
私達が教わってきた可動域の正常値と異なっていても本当の意味で可動域制限となっていないことがあると思います。その症例のアライメント、軟部組織の評価を行いどこまで可動域を求めるのか考察することが重要であると思いました。
明日からの臨床に活きるよう勉強していきたいと思います。
投稿者:天鷲翔太
2018年12月4日火曜日
関節運動の変化が関節軟骨・半月板に及ぼす影響について
今回は、関節の動態変化が関節軟骨にどのような影響を及ぼすかを述べた文献について紹介したいと思います。
村田健児他:関節運動の変化が関節軟骨・半月板に及ぼす影響.理学療法.24.77−83.2017
本研究は、メカニカルストレスとなり得る膝関節の運動学的異常が軟骨及び半月板に与える影響を検証しています。
対象は6ヶ月齢のラット40匹を用いられ、ACLを外科的に損傷させ、前方引き出しが過剰に生じている群(以下ACLT群)、同じく外科的損傷後、脛骨の前方引き出しを制動した群(CAJM)、通常飼育群(CTR)の3群に分類されています。
これらの3群を、術後12週目に関節軟骨と半月板の変性について組織学的分析を行われていました。
結果は、術後12週ではACLT群で関節軟骨厚の減少や関節軟骨の変性、表層のフィブリン化が他の2群と比較し、著しく重症化していました。
半月板の接触エリアと非接触エリアで比較すると、ACLT群とCAJM群の2群では双方のエリアで変性を認め、大腿骨側と脛骨側両方で変性が認められました。また、半月板自体の変性も同様に、ACLT群とCAJM群がCTR群と比較して有意に構造的破壊を認めていました。
以上のことから、膝関節の不安定性がある場合、関節軟骨や半月板に正常よりもメカニカルストレスが負荷となり、変性の重症化を招くことが分かります。
今回の研究では、ラットを用いて、ACL損傷による脛骨前方引き出しが制動されない膝関節を想定し、関節軟骨や半月板の変性がどう生じるのかを検討されていました。
ACLは膝関節内靱帯であり、膝関節の安定性の多くを担っています。関節の安定性は靱帯のみではなく、筋や腱、関節包など多くの軟部組織によって関節の安定性は保たれています。このメカニカルバランスが、生体内の組織(今回の研究では関節軟骨や半月板)が機能しやすい環境を整えていると言っても過言ではないと思います。
しかし、軟部組織の損傷や機能不全、筋の滑走不全やtightnessが存在した場合、本来の関節運動から逸脱した運動を行い、組織の損傷に繋がることが考えられます。
私たちが理学療法を提供させていただく方には、術後の方だけでなく、保存療法を選択された方に対しても理学療法を提供させていただきます。
opeによる介入が行われない患者様の理学療法では、軟部組織のバランスを整えることが重要となります。問題となる軟部組織を特定する評価や、それらに対しての治療技術など、さらなる技術向上や知識の積み重ねが必要となることが、改めて感じられました。
今週末に整形外科リハビリテーション学会主催のシンポジウムが開催されます。
詳細は当学会京都支部のHPからも確認できますので、皆様のご参加お待ちしております。
また、その他開催予定の全国研修会の詳細も確認できますので、そちらの方もよろしくお願いします。
今週末に整形外科リハビリテーション学会主催のシンポジウムが開催されます。
詳細は当学会京都支部のHPからも確認できますので、皆様のご参加お待ちしております。
また、その他開催予定の全国研修会の詳細も確認できますので、そちらの方もよろしくお願いします。
投稿者:高橋 蔵ノ助
2018年12月3日月曜日
【文献紹介】尺骨茎状突起骨折に対しての放置症例について
今回は、尺骨茎状突起骨折の何も介入を加えずに放置していしまった症例についての文献を紹介します。
対象
橈骨遠位端骨折に尺骨茎状突起骨折を合併した14名(15肢)
方法
15肢を尺骨茎状突起の先端部骨折と基部骨折に分類
疼痛の有無
骨癒合
尺屈回旋テスト
ulnar variance
について調査しています。
結果
先端部骨折と比較して基部骨折は偽関節を生じやすく、疼痛も残存しやすい傾向にあると報告されています。
また、疼痛を生じる例では、3mm以上のplus varianceを持つか尺屈回旋テストが陽性であったと報告していま
す。橈骨遠位端骨折の画像所見として尺骨茎状突起骨折の有無は画像所見として着目します。しかし、骨折の
有無だけでなく部位についても観察して行く事が大切なのではないかと感じました。さらに、尺骨茎状突起の
周囲にはTFCCや尺側手根伸筋腱などの軟部組織も存在します。その点に関しても注意して評価する事が多節
なのではないかと考えました。
久枝啓史、萩原博嗣・他:橈骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折放置例の治療成績・整形外科と災害外科.2000.49(2):p481-484.
登録:
投稿 (Atom)
人気の投稿
-
文献紹介 大腿骨転子部骨折において後外側支持欠損が lag screw sliding に与える影響 (徳永真己・他 : 骨折 第35巻、98-102、2013) 大腿骨転子部骨折をshort femoral neck (SFN) で...
-
本日は Bertolotti症候群について紹介させて頂きます。 Bertolotti症候群は1917年にBertolottiが提唱した症候群であり,最尾側の腰椎横突起が肥大し仙骨との 間に関節を形成,あるいは骨癒合した症例に腰痛が生じる症候群とされています。 ...
-
本日は、深臀部症候群(Deep gluteal syndrome 以下 DGS)に関与する 臀部ス ペース内の坐骨神経絞扼 について一部紹介させていただきます。 深臀部症候群(Deep gluteal syndrome 以下 DGS)は、 坐骨神経の...
-
人工膝関節全置換術(以下 TKA )後の理学療法では、屈曲可動域の増大や ADL の改善が主に進められていると思います。しかし、術後の伸展可動域や自動伸展不全(以下 extention lag )の有無が歩行能力や ADL に制限を生じるケースも少なくありません。 そこ...
-
本日は文献の中の距腿関節の接触面積について述べられている部分を紹介させていただきます。 君塚葵:足の生体力学.日本関節外科学会誌Ⅳ(1),1987:75〜85 新鮮切断肢を用いて検討されています。 中間位での荷重時接触面積を測定しています。 その結果、...